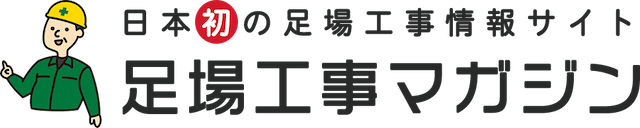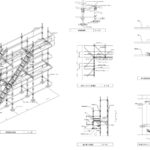福利厚生費は従業員の慰安、すなわち従業員のために使われる費用のことを指します。
つまり、常日頃から懸命に働いてくれている従業員をねぎらい、労働意欲の向上や現職への定着を促すことを目的として使われるお金が福利厚生費というわけです。
このことから、基本的に福利厚生費は従業員のために使われるお金という位置付けになりますが、個人事業主の場合はどうでしょうか?
たとえば、経営者でもあり従業員でもある一人親方や、個人事業で従業員として働く家族に対して福利厚生費は導入できるのでしょうか?

そもそも福利厚生費ってなに?
実は福利厚生費には2種類あります。
法定福利費と法定外福利費の2つです。
法定福利費は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」など、従業員が支払う金額の一部を会社側も負担する費用のこと。
法定外福利費は「住宅手当」「食事補助」「社内旅行の費用」など、業務には直接関係しない、従業員のために使う費用のことを言います。
このことから、福利厚生費は「従業員のために使う費用」という側面を持ち合わせていることが分かりますが、一人親方は従業員ではなく雇用主です。果たして、福利厚生費を使うことができるのでしょうか?
一人親方でも福利厚生費を導入できるの?条件は?
結論から申し上げると、一人親方は福利厚生費として経費計上することはできません。
理由は前述のとおり、福利厚生費は原則従業員のために使う費用だからです。
つまり、福利厚生費として経費を計上するためには家族以外の従業員を雇っていることが条件になります。
たとえば、完全に1人で事業を経営している場合や、家族経営などで従業員が配偶者などの家族しかいない場合は福利厚生費を計上することはできないので注意しましょう。
あくまで福利厚生費は、家族以外の従業員を雇用している場合のみに適用できると覚えておいてください。
ということで残念ながら、従業員を雇用していない一人親方は原則として福利厚生費を導入できないのですが、これから事業規模を大きくしていくつもりなら従業員を雇う機会も出てくるかもしれませんよね。
そこでここからは、家族以外の従業員を雇った時に役立つ知識として、福利厚生費として計上できる「経費の範囲」について解説していきたいと思います。
今はあまり関係ないかもしれませんが、この機会に理解し、頭の片隅に置いておきましょう。
福利厚生費として計上できる経費
一般的に福利厚生費と認められるためには「全従業員が平等に利用できること」及び「社会通念上妥当だと思われる金額の範囲内であること」という2つの条件を満たしている必要があります。
福利厚生費として認められる可能性が高い経費の例としては以下のようなものが挙げられます。
- 健康診断や人間ドックの費用
- 社宅の賃貸料
- 通勤費
- 社内行事(忘年会や新年会など)
それぞれ解説していきます。
健康診断や人間ドックの費用
従業員を対象とした健康診断や人間ドックの受診に掛かる費用は、福利厚生費として計上することが出来ます。
ただし前述の通り、全従業員を対象としていることや常識と考えられる範囲の金額であることが条件になります。
社宅の賃貸料
従業員が賃貸料の半額以上を負担していることを条件に、社宅の賃貸料を福利厚生費にすることも出来ます。
つまり、社宅を無償で貸し出した場合や従業員の負担が賃貸料の半額以下の場合は福利厚生費として計上できません。従業員の給与とみなされ課税対象になるので注意しましょう。
通勤費
職場へ通勤する際にかかる費用を補助する場合も、福利厚生費として扱うことが出来ます。ただし、通勤費には距離ごとにある一定の限度額が設定されており、その限度を超えると課税されてしまいます。通勤費の補助額は必ずその限度額に収まるように設定しましょう。
社内行事
忘年会や新年会など、社内で開催するイベントにかかる費用も福利厚生費になります。
また、同じく社内イベントとして社員旅行がありますが、こちらは少し特殊です。
なぜなら、社内旅行を福利厚生費として計上する条件として、旅行期間が4泊5日以内
であることと、全従業員の50%以上が参加することの2つが条件付けられているからです。
そして、やはりここでも「全従業員が平等に利用できること」及び「社会通念上妥当だと思われる金額の範囲内であること」がポイントになってきます。
もし、自己都合で旅行に参加しなかった従業員に金銭を支給した場合は給与支給とみなされ、福利厚生費として計上できなくなるので注意が必要です。
まとめ
今回は「一人親方でも福利厚生費を導入できるのか?」また、その条件や経費の範囲はどうなっているかについてご紹介いたしました。
家族以外の従業員を雇っている一人親方であれば、福利厚生費を導入することは可能です。
福利厚生費として認められるかどうかは「全従業員が平等に利用できること」及び「社会通念上妥当だと思われる金額の範囲内であること」の2点によって判断されますので、頭の片隅に置いておきましょう。